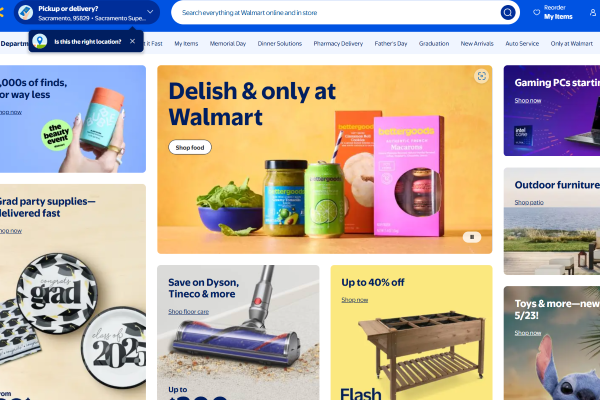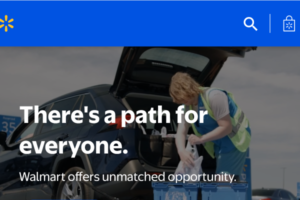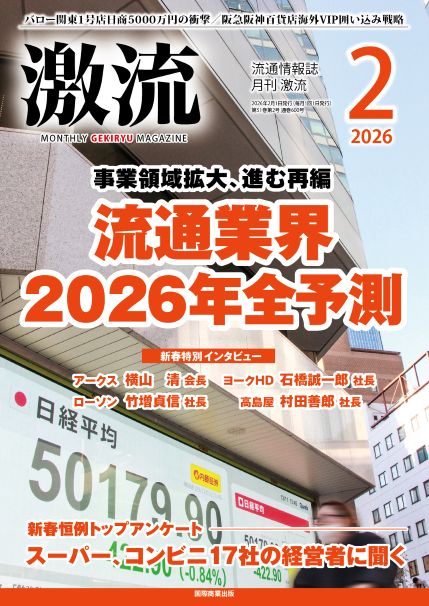5月15日、ウォルマートが2026年1月期第1四半期(2~4月)の決算発表を行い、最高経営責任者(CEO)のダグ・マクミロン氏と最高財務責任者(CFO)のジョン・デイビッド・レイニー氏が、米中を中心とした新たな関税政策、いわゆる「トランプ関税」に対する見解と、今後の対応方針について詳細にコメントした。
会見はアナリスト向けにオンラインで実施され、両氏は関税の発動タイミング、対象国、業種への影響、さらには在庫管理や価格設定への波及について具体的な戦略を示した。
食料品価格への波及は避ける
マクミロン氏は、「食品や消耗品の価格はできる限り低く抑えたい」と明言した。米国における食品価格は過去数年上昇が続いており、顧客は日常的にその影響を実感している。関税によるコスト圧力があるからといって、それを食品価格へ転嫁することは同社の基本方針に反するという。
実際、米国が新たに導入した対中関税とは別に、コスタリカ、ペルー、コロンビアといった中南米諸国への関税も、バナナ、アボカド、コーヒー、バラなどの輸入食品価格に影響を与えつつある。この点についてマクミロン氏は「廃棄率の抑制など、内部で制御可能な領域を徹底して管理することで、食品価格の安定を保つ」と語った。
また、サムズクラブにおける「母の日用の生花価格」を具体例に挙げ、「関税コストがかかっていても、価格据え置きで対応した」と説明した。
中国依存の現実と、生産地シフトの継続
関税の影響はすべてのカテゴリーに及ぶわけではない。ウォルマートでは、販売商品の3分の2以上を米国内で製造・組立・栽培されたものと位置付けているが、それでも玩具や家電といったカテゴリーでは依然として中国への依存度が高い。マクミロン氏は「中国は電子機器や玩具など一部カテゴリーで大きなボリュームを占めており、ここが最大の影響源となっている」と明言した。
その一方で、サプライチェーンの柔軟化は既に数年前から始まっており、素材をアルミニウムから関税のかからないグラスファイバーへ変更するなど、ミクロレベルでの対策も進められているという。生産国の変更も可能な範囲で続けており、これは一時的な措置ではなく、構造的な「脱中国化」に向けた中長期的な対応の一環である。
今回の関税政策において興味深いのは、ウォルマートが明確に「価格上昇は避けられない」と述べた点である。マクミロン氏は「価格を低く抑えるよう最大限努力するが、小売業界の利幅が限られている以上、関税をすべて吸収することは現実的ではない」と述べた。
また、関税の適用時期と在庫受領タイミングが業績に与える影響についても言及があった。同社は米国における在庫評価に「小売在庫法(RIM)」を採用しており、仕入れ価格の変動が即座に原価と利益率に反映される仕組みとなっている。これにより、「第2四半期には価格引き上げによる一時的な利益上振れが起きる一方、第3・第4四半期には売れ残りの値下げによる損益圧迫が発生する可能性がある」という。
新たな仕入れ地とリスク分散戦略
通商環境の変動に対応するため、同社は米国国内供給の比率引き上げと、輸入元の分散化を進めている。2021年には、10年間で3500億ドル規模の追加的な米国調達を表明しており、すでに実行に移されつつある。2024年には米国で2960億ドル分の商品を調達したという。
「グロー・ウィズ・アス」という中小企業支援プログラムも発表されており、米国内のサプライヤー育成と販路拡大が両輪で進行中である。また、同社のバイヤーが全米の新興ブランドを招いて直接交渉する「オープンコール」イベントも継続開催されており、長期的な供給網の多角化が戦略的に図られている。
レイニー氏も「こうした調達の地理的多様化が、関税リスクを長期的に緩和する助けになる」と語っている。
eコマースや広告へ収益源を移行
関税によるコスト圧力はあるものの、ウォルマートはeコマース、広告、会員制度といった高利益事業の拡大によって、構造的な利益率の改善を実現しつつある。第1四半期では、グローバルおよび米国においてeコマース事業が初めて黒字転換した。
また、広告事業「ウォルマート・コネクト」は前年同期比+31%、広告全体では+50%の伸長を示しており、ビジオ社買収の寄与も見られる。会員収入も二桁成長を維持しており、今後の営業利益構造における位置づけは一段と強まっている。
レイニー氏は「広告と会員だけで営業利益の約4分の1を構成している」と明かしており、今後はこれらの安定的・高利益な事業が関税や原材料コストの変動を吸収するクッションとなる見込みである。
ウォルマートの第1四半期の売上高は前年同期比+4%(為替一定ベース)、eコマースは+22%、ウォルマートUS既存店の売上は+4.5%、サムズクラブは+6.7%(燃料除く)と堅調に推移した。