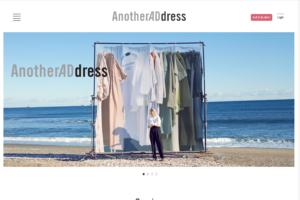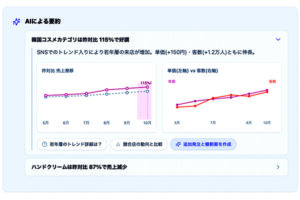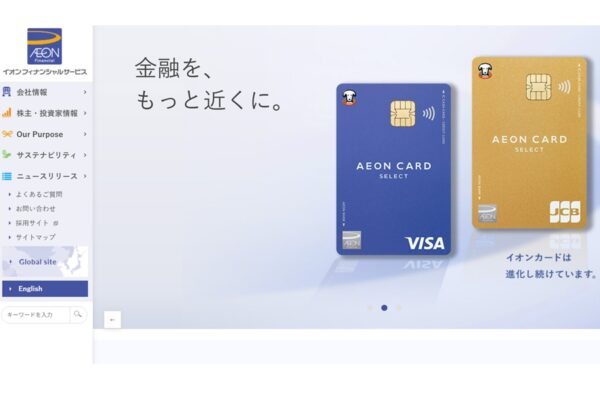インバウンド需要の蒸発が業績を直撃
百貨店業界にとって2020年は、まさに新型コロナウイルスに直撃された1年だった。
20年1~10月累計の百貨店売上高は3兆2000億円であり、前年同期比29.5%減少した。前19年は消費増税の影響で1.4%減の5兆7547億円と2年連続減少となったが、20年はレベル感がまったく異なる。通年で4兆円を超せるかも疑問視されるほどだ。ステージは完全に変わった。
当然ながら、20年も閉店ドミノは止むことがなかった。3月に新潟三越(新潟県)が閉店。そごう・西武も8月に岡崎店(愛知県)、大津店(滋賀県)、西神店(兵庫県)、徳島店(徳島県)の4店を閉店した。地方百貨店でも、1月大沼(山形県)、3月ほの国百貨店(愛知県)、8月中合(福島県)など有力百貨店の閉鎖が続き、山形県、徳島県からは百貨店が消滅した。
21年も2月にそごう・西武が川口店(埼玉県)、さいか屋が横須賀店(神奈川県)、三越伊勢丹ホールディングス(HD)が恵比寿店、9月に大丸松坂屋が豊田店の閉店を予定している。もちろんコロナ禍以前から閉鎖が決まっていた店舗もあるが、地方百貨店などコロナ禍が致命傷となったケースも多い。
海外店舗も戦線縮小が続く。三越伊勢丹は8月に旗艦店のタイのバンコク店を、3月にシンガポールのジュロンイースト店を閉鎖。東急百貨店もバンコク店を21年1月に閉鎖すると公表している。
百貨店各社の20年度上期業績は軒並み赤字に沈んだ。上場主要企業の売上高→営業利益(カッコ内は前年同期比もしくは前年同期の実績)を売上高順で見てみると、三越伊勢丹HDは売上高3357億円(41.8%減)→営業損益178億円の赤字(138億円)、エイチ・ツー・オーリテイリング3356億円(25.5%減)→44億円の赤字(63億円)、J.フロントリテイリング3195億円(41.5%減)→206億円の赤字(251億円)、高島屋2973億円(34.4%減)→102億円の赤字(134億円)、近鉄百貨店987億円(29.1%減)→21億円の赤字(21億円)、松屋205億円(54.1%減)→22億円の赤字(3億円)と惨憺たる数値が並ぶ(2月期もしくは3月期の中間決算、J.フロントはIFRS基準)。
コロナ禍で百貨店の構造的問題が噴出
コロナ禍の中で外食産業と並んで小売業の中で百貨店が極度に苦戦した直接的な要因は2点が挙げられる。一つは、これまで百貨店の数少ない成長のエンジンだったインバウンド需要の瞬間蒸発だ。19年に3188万人を数えた訪日外国人客数はコロナ禍が深刻度合いを深めるとともに2月58.3%減、3月に93.0%減と急減し、以後は99%前後の減少が続く。訪日客の累計総数は1~10月で400万人に過ぎず、前年比9割弱の減少となりそうだ。
大手百貨店の都市部主要店舗では19年度の免税品売上高比率が10%以上となり、大丸松坂屋の心斎橋店は約40%にも達していた。このため打撃は大きかった。20年度上期について三越伊勢丹(国内店合計)の免税品売上高は前年同期比95.2%減の16億9000万円。売上高に占める比率も6.6ポイント減り、わずか0.6%まで落ち込んだ。同様にJ.フロントも97.8%減の7億円で、比率も0.4%と惨憺たる状況。19年度のインバウンド比率が7%だった高島屋も、20年の売上高を前期比95%減と想定する。
鳴り物入りで登場した空港型免税店(訪日客向けに消費税だけでなく酒税やたばこ税も免除される空港型免税店)も縮小の一途だ。高島屋は新宿店で展開していた空港型免税店を10月に終了した。同店は年商計画80億円の未達が続いてきたが、コロナが致命傷になった。三越伊勢丹も福岡国際空港や西日本鉄道との合弁で16年4月から営業していた福岡店の免税店を7月に閉店。銀座店の免税店も一部商品を課税して国内客向けに販売し、さらに免税店内に国内客向けの売り場を作るなど、もはや免税店の意味を持たない状況になりつつある。

もう一つは、やはり顧客の生活様式の変化だ。4~5月の緊急事態宣言期間中には各社1.5カ月の休業を強いられたが、宣言解除後も9月まで月次売上高は20%前後の減収を続ける。顧客が多数集まること、また百貨店の最大の利点である対面販売のいずれもが感染拡大につながる懸念がある中では、大規模商業施設の象徴である百貨店から客足は遠のく一方だ。消費者の在宅勤務が常態化する中では都心部やターミナル駅に位置するほど集客ができず、旗艦店ほど苦戦を強いられた。
百貨店の強みは、その名の「百貨」の通り、豊富な品揃えにあったが、いまやネットショップの販売点数はそれを凌ぎ、アマゾンは億単位だ。ネットでは買い回りなどせずに瞬時に検索が可能。価格比較も1目瞭然だ。巣ごもり生活の中で、これが従来以上に認知されたと考えられる。 深刻なのは百貨店の利益を支える衣料の不振だ。外出機会が減れば高額なアパレル衣料を購入する必要もなく、在宅勤務ならスーツも不要。日用衣料ですべてが事足り、店頭は不良在庫の山となる。百貨店に強いアパレル大手のオンワードHDの20年度上期営業損益は114億円もの赤字となり、レナウンは5月に民事再生法を適用申請し経営破綻した(11月に破産法に切り替え)。
コロナ第3波で売り上げ回復期待は急速にしぼんだ
もっとも、百貨店の斜陽化は今に始まったことではない。1990年初頭のバブル経済崩壊とともに百貨店の市場規模は縮小の一途を辿ってきた。この間、明確な戦略なき合従連衡を繰り返してきたが、15年のアベノミクスと世界的なカネ余り、さらには近年のインバウンド需要の拡大に救われ構造的な問題の解決が先送りにされてきた。
百貨店の仕入れ販売は、長年、各社とも店頭で販売された段階で在庫に計上され、これが即売り上げに転化する「消化仕入れ」で行われてきた。百貨店は在庫リスクがゼロであり、廃棄ロスや値下げロスなどのリスクを強く意識しないで済む。これにより広い売り場を埋められる幅広い品揃えが可能となる。一方で販売されるまで商品の所有権はメーカー側にあり、このため品揃えや販促にメーカー側の意向も強く反映される。アパレルメーカーは販売員を店頭に派遣することも常態化し、これが百貨店にとっては店頭人員の抑制にもつながったとも言える。
だが、消化仕入れは諸刃の刃であり、メーカー側の意向の売り場への反映は、百貨店各社の売り場を均質化させるとともに、百貨店が自ら商品を調達する自主売り場の構築力の弱体化を招いた。コロナ禍の下、機動的な販売戦略の変更が必要だったが、メーカー依存体質ではこれは簡単ではない。
また在庫リスクを背負わぬ百貨店の利幅は薄い。各社、原価率は70%台の高さで営業利益率は2%内外に過ぎない。「損益分岐点は売上高の90%」(大手百貨店)であり、わずかな減収幅で利益が激減する。こうした構造的問題がコロナ禍で噴出したとも言えるだろう。
もちろんこれまで改革も進められてきた。J.フロントを筆頭にした“脱・百貨店路線”もその一つだ。要は定期賃貸借で運営する旗艦店「GINZASIX」に象徴される、百貨店のSC化だ。従来のショップと定借契約を結び、館や売り場を譲り渡す。自社の百貨店の店舗も1テナントとの位置づけになり、物販・小売業よりも運営・不動産業の色彩が強まる。不動産収入が軸となり、売上高・粗利の歩合収入もあるが、固定賃料部分があるため収益は安定する。自社の商品改革や売り場改革による成長を断念した戦略と言えるだろう。
丸井のショールーム路線に大手百貨店も倣う動き
これに対し、三越伊勢丹は新宿店などの改装を通じて従来型百貨店の店頭豪華路線を突き詰めた“真・百貨店路線”を進めた。だが、17年のトップ交代を契機に路線を転換し、遅ればせながらSC化路線に加わり、主要各社はこぞってSC化を進めてきた。ビックカメラや東急ハンズ、ユニクロなどをテナント導入し、先行するJ.フロントは店舗改装を通じ子会社の都市型SC、パルコを上野店や心斎橋店に次々導入、SC化を加速させている。
しかし、そのJ.フロントにしても20年度上期は最終赤字決算を免れなかった。不動産部門とパルコ部門のセグメント損益の合算はマイナス10億円で前年同期115億円から急降下した。コロナ禍ではSCも客足は激減する。歩合収入は低下するうえ、テナントの家賃減免要請にも応じざるを得ない。全社的に見れば、物販に比べ不動産賃料は収入が低いため、人件費を中心にした固定比率が高くなる。SC化に伴い発生する余剰人員の行き場やルミネに代表される駅ビルや大手不動産系SCなどとの競合など課題も多い。SC化路線の成否を判断できるのは、なお先になるだろう。
真・百貨店、脱・百貨店に続き注目される戦略が、丸井が進める「ショールーム路線」だ。丸井は15~16年にSC化を一足早く終えると、次には店頭にスーツやシャツの「FABRICTOKYO」、ECプラットフォームを運営するBASE、最新ガジェットを販売するb8ta(ベータ)、メルカリなどD2C(ダイレクト・トゥ・コンシューマー)業者の導入に力を入れてきた。コンセプトは「売らない店」。顧客がこうした体験型店舗で商品を体験し、ネットで購入するビジネスモデルだ。こうした体験型店舗は19年度末にテナントの38%に達している。さらには23年度末までにこの比率を逆転させ、6割にまで拡大させる目標だ。
これが丸井1社だけの試みならば丸井の奇策と片付けられるが、大手百貨店もこれに倣う動きがある。たとえば阪急阪神百貨店は10月にワイン祭を行ったが、レジはなく試飲のみ。販売は同社のECサイトのみだった。コロナ禍でレジ前の3密を避ける狙いだったが、一つの契機になるかもしれない。三越伊勢丹は「地方店には今後デジタルサロンをつくりながら、首都圏の商品をそこでお客様にご案内できる場所をつくり、しっかり接客してデジタルでモノを売るという役割に変わっていくのではないか」(同社首脳)とする。地方店ではすでに本店とテレビ電話システムをつなぎ、本店の商品を地方店のサロンに集客した顧客層に見せて販売する試みが行われている。これが本格化すれば地方店の売り場が大きく減るが、「地方店はモノを売るよりも、(顧客層に)食品、レストラン、カフェ、体験活動などで時間を消費してもらう」(同)という。
都心部のリアル店舗とネットとの融合戦略は、ネット専業の小売業者には真似できない。これが定着すれば、百貨店に来店したことすらなく買い物はネットとコンビニで済ませる若年層を取り込む呼び水になる可能性も秘めている。
ただ〝鶏が先か、卵が先か〟の議論でもあるが、そのためにも百貨店のECサイトの底上げが不可欠だろう。20年度のEC売上高見通しは、三越伊勢丹が310億円、高島屋が270億円だ。ようやく善戦し始めたとも言えるが、20兆円弱の市場規模から見れば存在感は小さく消費者の認知度は低い。三越伊勢丹は20年度内に取り扱い品目を10万点から15万点に増やす方針だが、それでも店頭の7割程度に過ぎない。店頭にはない限定商品や店頭と同等の品揃えがない限り、なかなか消費者を百貨店ECに呼び込めない。現状、アパレルメーカーにとっては、自社サイトもアマゾンもZOZOもある中で、売れない百貨店サイトにわざわざ商品を提供するメリットが欠ける。
コロナの動向如何にかかわらず百貨店業界に課題は山積している。そんな中で10、11月には緩んだ雰囲気が広がった。10月単月の売上高が1.7%減と、高額品の好調から回復傾向が鮮明になってきたためだ。しかしながら、19年10月は消費増税直後で前年同月比17・5%減と発射台が極端に低かった。期待は1カ月経って急速にしぼんだ。コロナ第3波から大手百貨店の売上高は軒並み10-20%減の水準に逆戻りした。
21年も百貨店の苦境と試行錯誤は続く。国内客足やインバウンドが一時的に戻ることはあるだろうが、構造的問題に向き合わず、かりそめの回復に踊るならば、百貨店業界の縮小は加速する一途だろう。