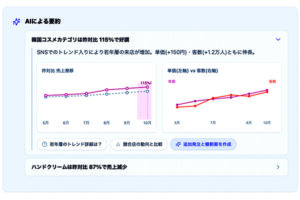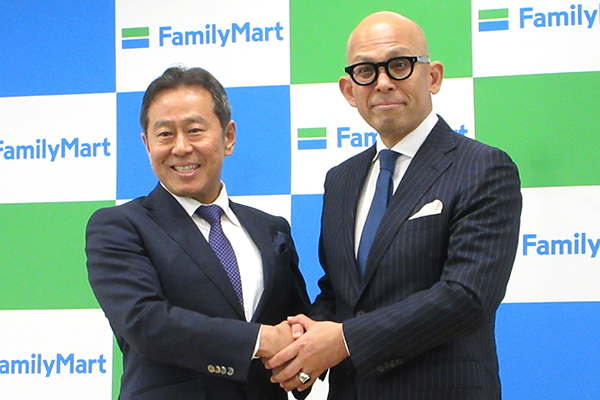明治の文明開花から続く「横並び」現象
毎朝、新聞を開けばDX(デジタルトランスフォーメーション)という単語を見ない日はない。企業においては、トップも現場も口を開けば「DXに取り組まなくては」と言う。今や「DXとは何ですか」とは恥ずかしくて聞けないほどだ。
今、「2025年の崖」が叫ばれている。これは、老朽化する既存のITシステムを刷新しなくては、数年後には崖っぷちに追い込まれるリスクを意味している。このため、18年に経済産業省は「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」を発表し、刷新するとともに、データとデジタル技術を活用して、激変するビジネス環境に対応できる新たなビジネスモデル、組織、企業文化を構築するよう促している。様々なビジネスモデルがITと連動している昨今、DXが重要であることは否めない事実である。
皮肉にもDXの背中を押したのはコロナ禍だった。医療機関と保健所間の連絡が未だにファクスで行われていたことがきっかけの一つとなり、今年9月1日にデジタル庁が設立される予定。加えて、企業でテレワークが広まり、情報戦略を熟考、再考する契機になった。これらの影響もあり、あの会社はDXを強化しているから当社も、という「横並び」現象が散見されるようになった。見直し機運が高まったこと自体は良かったが、DXがなんでもかんでも解決してくれると錯覚する楽観論が蔓延しているように思われる。
だが、この楽観論に警鐘を鳴らすような事件が相次いだ。20年10月1日に発生した東京証券取引所の株式売買システムの障害に続き、3月3日には、みずほ銀行でネットワークが一時途切れ、東京都や千葉県、大阪府などにあるATM29台が止まってしまった。

日本企業は、お上のお墨付きや大手マスコミが叩く太鼓に踊らされる節がある。さらに「欧米では」、「シリコンバレーでは」という修飾句が加われば、より敏感に反応する。この「横並び」現象は、明治の文明開化以降変わっていない。
どうも、日本人は隣に合わせなければ心配で仕方がないようだ。単なる印象論ではなく、学術的な調査でも、この原因が明らかになっている。
慶應義塾大学大学院の前野隆司教授の研究によると、日本人は不安を感じやすい民族であるという。人は、脳内化学物質のセロトニンが脳内から減ると、不安を感じたり、気分が落ち込んだりしやすくなる。セロトニンの分泌量を左右するのが、「セロトニントランスポーター遺伝子」。この遺伝子にはセロトニンの分泌量の少ない「S型」と、分泌量の多い「L型」の2種類があり、その組み合わせによって、不安を感じやすい「SS型」、楽観的な「SL型」、その中間である「LL型」の3つに分かれる。日本人の遺伝子はSS型が65%を占めているのだ。一方、欧米人は、SS型が19%、SL型が49%、LL型が32%となっている。
ダイエー中内氏、ソニー出井氏の先見性
心配性の日本人でありながらも大胆な決断をし、それがうまくいくと「先見性に富んだ名経営者」と言われる。奇しくも、「液晶のシャープ」としてこの世の春を謳歌していた04年、同社の町田勝彦元社長に「経営者にとって最も大切な資質は何ですか」と問うたところ、「先見性です」と断言した。「国内で販売するテレビを、05年までにブラウン管から液晶に置き換える」と宣言したほど、自身の先見性を信じて疑わなかった。
しかし、韓国、台湾企業の台頭により、液晶パネル市場の競争が激化し、さらにリーマンショックが追い打ちをかけ、同社は経営危機に見舞われる。好調なときには功を奏した「選択と集中」が、一旦風向きが変わると経営不振に陥るほどの大きなリスクとなった。
この結果、16年4月2日、台湾に本拠を置く鴻海精密工業が2/3弱のシャープ株を取得し、日本の大手電機メーカーとしては初の外資傘下の企業となる。だからと言って、町田元社長に先見性がなかったとは断罪できない。この頃、ジャーナリスト、アナリスト、経営学者、そして多くの経営者も「シャープは良い会社になった」と評価し、社員も「経営者に恵まれている」と安心していたのだから。
同じような事例が流通業界でも見られた。ダイエーの創業者である中内㓛氏は、スーパーマーケット(SM)という業態を日本で最初に実現し、1972年には売上高で三越を抜く。「流通革命の旗手」は日本の「流通王」に上り詰めた。
80年には日本の小売業では初めて売上高1兆円を達成した。が、バブルの崩壊により、購入した土地を担保に資金を集めて大規模店を建てるというビジネスモデルが機能しなくなり、積極的な拡大路線がとん挫した。さらに、阪神・淡路大震災も重なり経営不振に追い込まれ、15年1月よりイオングループの一員(完全子会社)となった。

このような外的要因がダイエー凋落の大きな原因と見られているが、それ以上に消費者のニーズが多様化したことにより、「よい品をどんどん安く より豊かな社会を」という中内氏の考え方だけでは通用しなくなっていた。「流通革命の旗手」は新たな流通革命により、覆させられたことになる。
ユニクロ(ファーストリテイリング)のようなSPA(製造小売業)と呼ばれるアパレル専門店が台頭したのは、デフレ社会の副産物と見られているが、中内氏が重視した「価格の安さ」だけでなく、それにプラスアルファを求める消費者の心理的変化が背景にある。この現象を筆者は「懐は庶民、心はセレブ」と表現している。
中内氏は目前の市場分析に苦慮していたものの、未来を見る目は衰えていなかったようだ。生前、自身が設立した流通科学大学(神戸市)で講義をしたとき、次のように発言している。
「これからは、冷蔵庫にパソコンが内蔵され、インターネットにつながれば店舗は要らなくなる」と。時代は、大方その通りになった。ところが、残念ながら、それを実現したのは、楽天やアマゾンであった。
歴史に「もし」はないと言われるが、バブルの崩壊、阪神大震災がなければ、中内氏が撒いた種のいくつかが新たな成長事業として開花していたかもしれない。
最近、再会し久しぶりにインタビューしたソニーの出井伸之元CEO(現クオンタムリープ会長ファウンダー)も、天国と地獄を見た経営者と言われる。中内氏と同様、先見性という点で評価できる点も少なくなかった。そんな出井氏も、アップルコンピュータのiPod、iTunesにウォークマンのお株を奪われ、03年4月に同社の株価が急落した「ソニーショック」に直面する。その後、経営再建計画の達成が難しくなり退陣を余儀なくされた。
出井氏はインターネットの可能性に注目し、ネットワーク時代のソニーグループの礎を築いた。森喜朗政権時代の00年7月にはIT戦略会議議長に就任し、ブロードバンドの普及を提唱した。
出井氏が撒いた種は、今、開花している。ソニーは2月3日、21年3月期連結業績予想を修正し、純利益を昨年10月の前回予想から2850億円多い1兆850億円になりそうだと発表した。純利益では初めて1兆円を突破し、2年ぶりに過去最高益を更新する見通しだ。
ちなみに、現在、ソニーのCEOを務める吉田憲一郎氏は、出井社長時代に社長室長を務め、出井氏の経営を傍で見てきた。出井氏はV字回復で立役者を務めた吉田氏の「家庭教師」であったと言えよう。
出井氏曰く「今は変化が速いですから、非連続にならざるを得ません。3年計画なんて立てられないです」。
勇気ある小心者が経営者の資産
では、DXを推進している経営者の先見性はいかがなものか。「1億総DX」現象を見ていると、インターネットが普及する前に起こった80年代前半の「ニューメディア」ブームを彷彿させる。新しい経営用語が流行り出すと、経営者の目には、それが諸問題を解決する魔法の杖のように映る。トップが「DXを推進せよ」と命じても、現場は空回りし他社の模倣をするだけで、トップから文句を言われない程度の改革でお茶を濁す。そのため、差別化できるほどの経営戦略、ビジネスモデルに繋がっていないようだ。
DXがうまくいかない根本原因は何か。その最大要因は、経営者自身が、「魔法の杖」を理解していないからだ。おまけに、「魔法の杖」を使える組織も存在せず、人材もいない。その結果、「魔法使い」を標榜する専門業者に丸投げしてしまう。これでは、従業員たちは、「いったいうちの会社は何をしようとしているのだろうか」と戸惑うばかりである。
昨今、「両利きの経営」という言葉を耳にした人は多いだろう。チャールズ・A・オライリー・スタンフォード大学経営大学院教授とマイケル・L・タッシュマン・ハーバードビジネススクール教授が構築した経営学の理論だ。その要旨は、次のとおり。
新規事業と既存事業の経営戦略が異なることは言うまでもない。新規事業は道の新分野を開拓する「知の探索」がカギを握る。一方、既存事業では、現在ある経営資源(ヒト、モノ=サービス、カネ、情報)を効率的に活用する「知の深化」が求められる。探索と深化をバランスよく両立できるのが「両利きの経営」である。実は、老舗企業には「両利きの経営」で成功しているところが多い。
流通業界に目を向ければ、イオンのルーツである呉服屋だった岡田家には、「大黒柱に車をつけよ」という家訓がある。環境の変化に対応して企業自体を変革させよという意味だ。
岡田屋は呉服店に始まり、戦後、食品を扱うスーパーマーケットになった。その後、GMS(総合スーパー)、専門店、SC(ショッピングセンター)、クレジットカードなど、あくまでも流通業を大黒柱とし「知の深化」を心がけながらも、時代と共に大きく変わる繁盛する場に大黒柱を移す「知の探索」を行ってきた。この経営戦略が、今のイオングループという形につながったと考えられる。
DXを推進するにあたっては、それを革命的改革につながる「魔法の杖」と信じ込むのではなく、まずは、「知の深化」をはかるためのツールとして部分的に試してみるべきである。そうしているうちに、解決しなくてはならない問題が山積されていることに気づくことだろう。
その一方で、「知の探索」も継続的に行っていかなくては未来がない。そこで「先見性」が求められるわけだが、「人間、明日のことさえ分からない」という謙虚さを忘れてはならない。私には先見性があるからまちがいない、と思うところに落とし穴が隠されている。
今、経営者がもっとも注目する経営者とされている日本電産の永守重信代表取締役会長(最高経営責任者)は、積極的なM&Aにより急成長を果たしたことから、かなり大胆な経営者だと思われているが、「経営者は小心者のほうが成功する」と話している。
「知の探索」は試行錯誤が求められリスキーである。だからと言って、単なる小心者にとどまっていては明るい未来が開けない。「勇気ある小心者」にならなくてはならない。相反するような言い方になるが、DX投資の勇気を出すためにも、確実性が高い既存事業でしっかり儲けておく必要がある。
とはいえ、既存事業で大成功を遂げてしまうと、経営者は「知の深化」ばかりに目が行くようになる。それが不調になった時、がたがたと崩れ落ち経営危機に陥ってしまう。いわゆる「サクセストラップ(成功の罠)」というものである。前述のシャープは、液晶にかけ過ぎた。町田元社長に「液晶の次は何を考えていますか」と聞くと、「液晶の次は液晶」という言葉が返ってきた。この思考が、同社の首を絞めたのだ。
このようにならないためにも、難しいことではあるが、「知の深化」と「知の探索」の両立が求められる。DXにおいても、既存事業を改善し食い扶持をしっかり確保するために活用する一方で、こんなに多額な投資をしても大丈夫なのか、と慎重になりながら、新事業のビジネスモデルに組み込んでいくことを勧めたい。