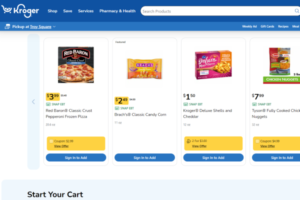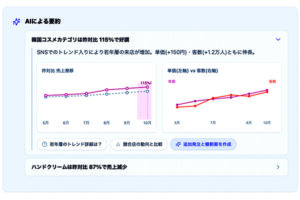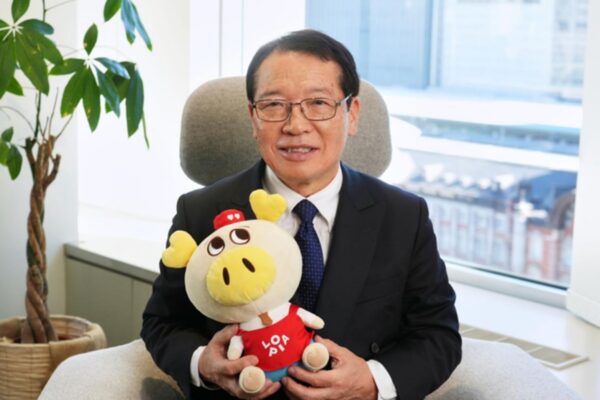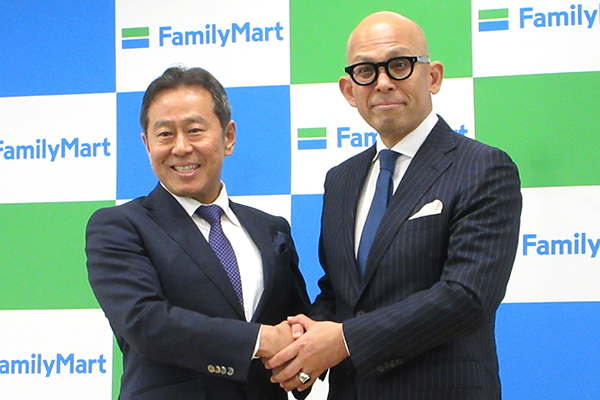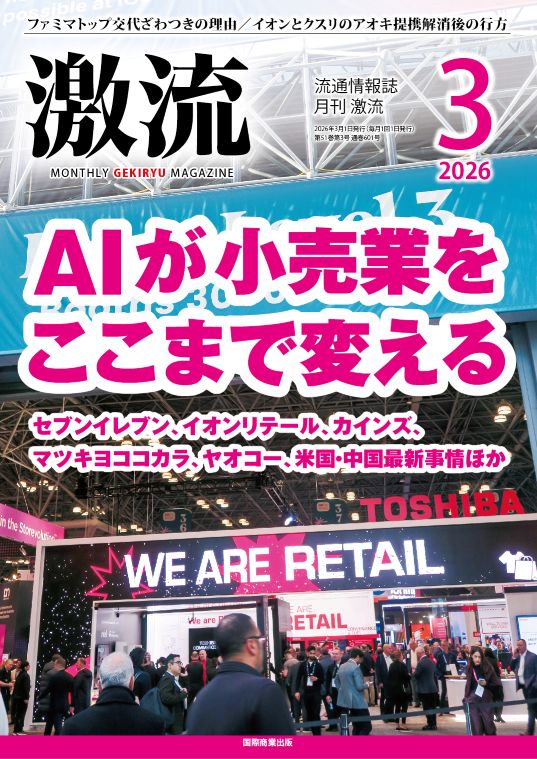クローガーは今年も障害者雇用に関する最高評価を獲得し、6年連続で「障害者インクルージョンに優れた職場」に認定された。評価は、非営利団体ディスアビリティ・インと全米障害者協会(AAPD)が共同運営する「Disability Equality Index®(障害平等指数)」に基づいている。
クローガーの上級副社長兼チーフ・アソシエイト・エクスペリエンス・オフィサーであるティム・マッサ氏は、「クローガーは、すべての能力を持つ従業員が意義ある貢献をし、成長できる職場の実現に強くコミットしている」と述べた。
インクルージョンが「経営戦略」に
Disability Index®は、企業の障害者インクルージョンに関する方針・実践・成果を評価・数値化する包括的ベンチマークツールである。2025年版では、アメリカ、日本、ドイツ、インドなど8カ国から655社以上が参加し、インクルージョンに関する取り組み状況を報告。
その結果、柔軟な働き方、物理的バリアフリー、障害に関する非差別方針の明示、従業員リソースグループ(ERG)の設置といった施策が、参加企業の多数で標準化されつつあることが明らかとなった。
たとえば、「従業員支援プログラム(EAP)」を導入している企業は24年の73%から25年には99.7%に急増した。また、面接時に配慮が必要であることを候補者に伝える企業も37%から66%へ、短期障害給付制度の導入も48%から94%へと大幅に伸びている。企業が単なる法令遵守の枠を超え、障害者インクルージョンを人材戦略や経営基盤に組み込んできた証左である。
クローガーでも従業員による自発的な障害の自己申告を促進し、社内の支援体制を可視化するほか、アクセシビリティ課題に対応する専任担当者を配置し、社内システムの定期的なアクセシビリティ監査やユーザビリティ調査も行っている。
加えて、クローガー・テクノロジー&デジタル部門のプロダクトマネージャーであり、障害者ERG「Our Abilities」の共同議長であるルーシー・マルコヴィッチ氏は、「クローガーでは誰もが自分らしくいられ、意見が尊重される環境が整っている。自分の声が活かされる職場を求めるなら、私たちの仲間になってほしい」と呼びかけた。
AI時代の障害者インクルージョン
25年のDisability Index®では、障害者がAIなど新技術の適応において非障害者よりも早く習熟しているという新たな傾向も指摘されている。AIを含むデジタル領域のアクセシビリティが、企業のイノベーションを加速する手段となりつつあり、アクセシビリティ専門人材の配置やベンダーへのアクセシビリティ要件適用も今後の成長機会とされている。
一方で、従業員の障害自己申告率は国際的に3.5%、新入社員に限っても4%と依然として低い水準にとどまっており、企業には信頼醸成とプライバシー配慮を両立する工夫が求められている。調査では、予算の中央集権化やマネージャー研修の充実、ガバナンスへの統合といった取り組みが持続可能なインクルージョンの鍵を握る、とまとめられている。
クローガーはニューズウィークによる「米国で最も信頼される企業」や「ダイバーシティに優れた職場」にも選出されており、多様性と包摂性を企業価値の中核に据えた経営を進めている。
ディスアビリティ・インは障害者インクルージョンに特化した世界的な非営利組織であり、フォーチュン100企業の70%以上がDisability Index®に基づき年次評価を行っている。26年にはより柔軟で、業種別ベンチマークやESG報告との連動を視野に入れた新指標として提供される予定だ。
日本では現在、常用労働者40人以上の企業に雇用義務があるが、26年7月から対象企業規模が「37.5人以上」に拡大する。同時に法定雇用率も2.4%から2.7%へ引き上げられることになっている。自社の経営戦略の柱の1つに据えられるかどうかで、実効性が試されそうだ。