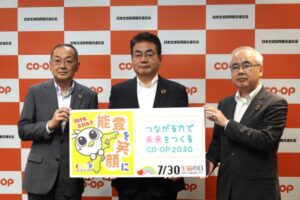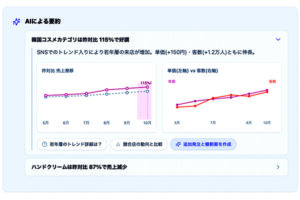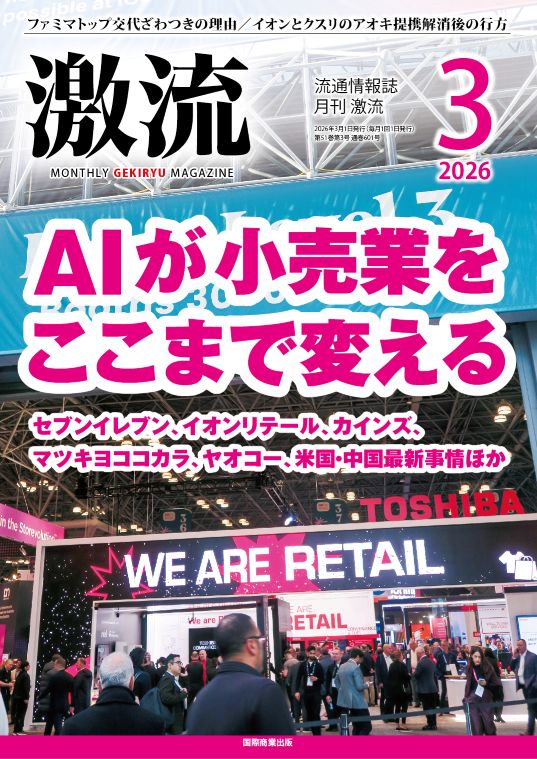食品スーパー業界再編の目玉となるか――。ヤオコーは10月1日、親会社ブルーゾーンホールディングス(BZHD)を設立し、持株会社体制に移行した。ヤオコーの単独株式移転と、ヤオコーが保有していた子会社株式の現物配当により、BZHD傘下に100%子会社のヤオコー、エイヴイ、フーコット、ヤオコービジネスサービス、小川貿易、ヤオコーハーモニーの6社と、66%を保有する子会社せんどうがぶら下がる形となった。
ここまでは既定路線だが、業界を驚かせたのは同日発表の食品スーパー2件のM&Aだ。一社は都内に14店、神奈川に5店を展開する文化堂(本社:東京都品川区)で、10月16日完全子会社化を実施。もう一社は「クックマート」を愛知に8店、静岡に4店展開するデライトHD(本社:愛知県豊橋市)で、こちらはヤオコーが10月31日付で70%を出資する。文化堂は25年5月期の売上高が278億円、営業利益が8億8400万円。デライトHDは25年3月期の売上高が354億円、営業利益8億4100万円で、単純に見ればBZHDの規模が約600億円膨れ上がる。
この2社のM&Aが意味するところは、まずヤオコーが弱い東京都内を攻める姿勢を見せたところだ。文化堂は都内でも駅前立地などに比較的小型の店舗を構えており、これから自前での都心開拓が難しい中、店舗網と都心での営業ノウハウを取得できるメリットがある。
もう一つは関東圏のリージョナルSMというポジションから、デライトHDを傘下に収めることで静岡、愛知へとドミナント領域を広域に広げたことだ。これにより、同業に対して「関東圏でなくとも組む可能性がある」とメッセージを発したことになる。
今後注目すべきはやはりグループシナジーだろう。持株会社体制に移行した狙いについて、BZHDの川野澄人社長(ヤオコー社長兼務)は、「ヤオコーが親会社であるよりも他の事業会社と兄弟のほうが互いに学びやすい」と語っている。生鮮の売り方や惣菜の開発などで互いにノウハウを共有しやすいということだろう。一方で取引先政策の一本化など、仕入れにおけるスケールメリットの発揮については「考えていない」と今年5月の決算説明会の席上発言している。SMとDSでMD政策が異なるためがその理由だが、これも規模が大きくなれば、DSを除くSM企業だけでスケールメリットを発揮できる可能性もある。伸び代はまだまだありそうだ。
(冒頭写真は、文化堂の川崎店)