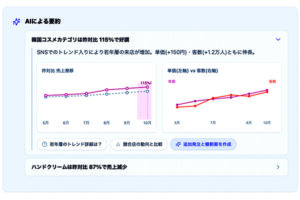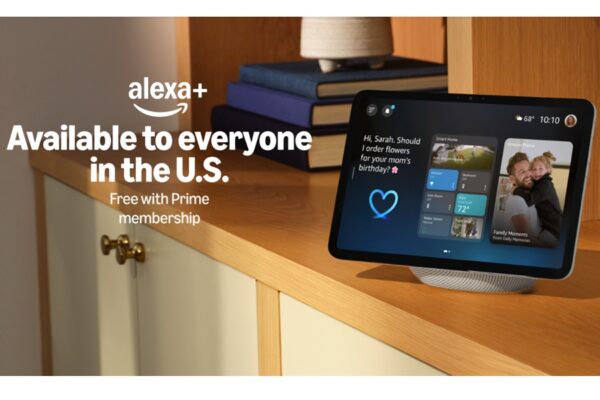キッコーマンは6月9日の米国第1工場稼働50周年記念式典に先立ち、7日に記者懇談会を開催した。
同社は1957年、カリフォルニア州に販売会社を設立。しょうゆの認知を高めた一方、現地での製品化を進め、67年の瓶詰め作業開始に続き、73年にウィスコンシン州ウォルワースで第1工場を稼働させた。これが北米事業拡大の契機となり、海外事業全体の牽引役となった。キッコーマンは現状、売上高の7割、事業利益の8割以上を海外事業で占めている。
懇談会で茂木友三郎名誉会長(写真)はこれまでの海外事業の原動力について、商品が東洋的な料理だけでなく西洋料理にも使える万能性、また早くからアメリカに進出したことで「(アメリカ人に)自分たちの商品だという気持ちを強く感じてもらったこと」(茂木名誉会長)、ビジネスセンスのある社内人材を送り込んできたこと、と分析。今後の海外事業については「しょうゆ自体が伸びる余地は大いにある」と明言。米国ではキッコーマンを含めたしょうゆを利用する世帯が現状6割であることから、次の50年でこれを100%にしていきたい考え。またヨーロッパ、アジアの伸びに加え、南米、インド、アフリカでの事業拡大と合わせて、ソイミルクの拡販など事業の多角化も進めていきたいと語った。

そのほか、記者との主なやりとりは次の通り。
――50年間で撤退を考えたことはあったか。
茂木:撤退が頭をよぎったことは一度もない。ただし非常に大変だと思ったのは石油ショック。1973年6月にアメリカ工場ができ、その年の秋に起きた。狂乱物価で原料がどんどん上がり、商品の値段が追いつかなかった。最初の年は大赤字で、次の年はもっと大赤字。私が考えた赤字よりも遥かに大きくこれには参った。しかし価格が追いついてくればなんとかなるだろうというふうには思っていた。実際価格水準が合ってきたことで利益が出て4年でなんとかなった。ヨーロッパでも考えたことはないが、(食文化が)保守的でなかなか伸びなかった。もっと工場を早く造りたかったが、私の想定より10年遅れた。当初はいくら努力しても(厳しかったが)、ヨーロッパも徐々に異文化を取り入れる許容度が広がっていったこと、セールスのできる担当を連れて行ったことが良かった。
――インドやアフリカなど、スパイス文化の国々でしょうゆの浸透は難しいのではないか。
茂木:食文化の違いで言えば、ヨーロッパもアメリカもそう。食文化の交流は時間をかけないとだめ。焦ってやると逆に嫌われてしまい、拒否反応が出てしまうとかえって上がりにくくなる。なのであまり焦らず慎重にやっていかないといけない。ただ、食文化の違いがあるからだめということではなく、将来的にはその文化が変わってくるかもしれない、融合ができるかもしれないと思っている。
――人口減でシュリンクする国内市場をどう見ているか。
茂木:国内は伸ばさないといけない。海外比率が売り上げの70%、利益の80%というのは若干多すぎる。人口減は日本の国自身にとっても大変なことで、これから30年後、50年後を考えると非常に心配。もっと人口を増やすことを考えていかなければ、増えないまでも減り方を少なくしないといけない。私どもはたまたま海外のウエートが大きいので割合影響を受けていない。ただ食品会社は口の数で総需要が決まってくるので、様々な産業があるが、食品会社は大変になる。国内では安売り競争をやめて付加価値のあるものを作っていかないとみんな共倒れになってしまうのではないか。それは食品全体として反省するべきことだと思う。